花嫁衣装の掛下:伝統と個性を彩る

ウェディングの質問
先生、「掛下」って着物の一種だと思うんですけど、どんな着物なんですか?

ブライダル研究家
いい質問だね。「掛下」は花嫁衣装の一つで、打掛の下に着る振袖のことだよ。打掛を着るときには必ず掛下を着るんだ。

ウェディングの質問
へえ、そうなんですね。じゃあ、掛下はどんな色が多いんですか?

ブライダル研究家
基本的には白地が多いね。でも、最近は色打掛や、お色直しで着る和装に合わせて、白以外の色の掛下を合わせることもあるんだよ。
掛下とは。
婚礼衣装の用語である『掛下』について説明します。『掛下』とは、花嫁衣装の一つである打掛の下に着る振袖のことです。掛下は、打掛の色合いに合わせて選びます。通常は白地の振袖を用いますが、色鮮やかな打掛や、式の中で衣装を変える際に着る新しい和装の場合は、白以外の色の掛下を組み合わせることもあります。掛下を着るときは、着物の裾を短く折り曲げずに、長く引きずるように着付けます。
掛下とは

掛下とは、日本の結婚式で、花嫁が着る打掛の下に着る着物のことです。 花嫁衣装の一部であり、打掛をより美しく見せる役割を担っています。いわば、主役である打掛を引き立てる名脇役と言えるでしょう。掛下は、単なる下着ではなく、花嫁の美意識や個性を表現する大切な要素です。
掛下は振袖の形をしています。色や柄、素材は様々で、白無垢や色打掛といった打掛の種類に合わせて選びます。白や赤、金など華やかな色合いのものや、四季の花や吉祥文様などの伝統的な柄、鶴や亀などの縁起の良い動物が描かれたものなど、実に多くの種類があります。素材も、絹や錦など高級感のあるものが用いられます。最近では、洋風の要素を取り入れた現代的なデザインの掛下も人気を集めています。
掛下選びは、花嫁にとって結婚式準備の中でも楽しみの一つです。打掛との組み合わせによって全体の印象が大きく変わるため、自分の好みに合った掛下を選ぶことが大切です。例えば、白無垢には白や赤の掛下を合わせるのが一般的ですが、淡い色の掛下を選べば、より清楚で優しい印象になります。色打掛には、打掛の色と相性の良い色や柄の掛下を選び、全体の調和を考えながらコーディネートを楽しむことができます。
掛下は、普段は見えない部分ですが、袖口や裾から見える掛下の色や柄が、全体の装いに奥行きと華やかさを加えます。写真撮影の際に、ふとした仕草で掛下が見えることもあります。そのため、掛下選びにもこだわり、自分らしい装いを完成させることが、より思い出深い結婚式につながると言えるでしょう。まさに、花嫁の個性を彩る隠れた主役と言えるのではないでしょうか。
| 掛下とは | 日本の結婚式で、花嫁が着る打掛の下に着る着物 |
|---|---|
| 役割 | 打掛をより美しく見せる、花嫁の美意識や個性を表現する |
| 種類 |
|
| 掛下選びのポイント |
|
| 掛下の効果 | 袖口や裾から見える掛下が全体の装いに奥行きと華やかさを加える |
| まとめ | 掛下選びにもこだわり、自分らしい装いを完成させることが、より思い出深い結婚式につながる |
掛下の色と柄

掛下は、花嫁衣装の打掛の下に着る着物です。その色と柄は、花嫁の美しさを引き立てる重要な要素となります。古くから、掛下は白が基本とされてきました。白は、純粋無垢な心を表し、日本の伝統的な婚礼にふさわしい色と考えられてきました。特に白無垢には、白地の掛下が合わせられるのが一般的です。白一色の清らかな組み合わせは、神聖な雰囲気を醸し出します。
しかし、近年の結婚式では、色打掛や、現代風にアレンジした新しい和装スタイルが人気を集めています。それに伴い、掛下にも様々な色のものが登場し、花嫁の選択肢が広がっています。例えば、赤や桃色は、華やかで祝いの席にふさわしい印象を与えます。金色や銀色は、上品な輝きで花嫁をより美しく引き立てます。これらの華やかな色の掛下は、色打掛との組み合わせによって、より一層華やかさを演出することができます。
掛下の柄も、花嫁の個性や好みに合わせて選ぶことができます。古来より伝わる縁起の良い模様である鶴や亀、松竹梅などの古典的な吉祥文様は、 timeless な美しさで人気があります。また、四季折々の花々や、現代的なデザインを取り入れた柄など、多様な選択肢があります。掛下の色や柄を選ぶ際には、打掛との調和が大切です。打掛と掛下の色や柄の組み合わせによって、全体の印象が大きく変わります。例えば、華やかな色柄の打掛には、落ち着いた色合いの掛下を合わせることで、全体のバランスを整えることができます。反対に、シンプルな打掛には、華やかな掛下を合わせることで、アクセントを加えることができます。このように、掛下の色柄と打掛を調和させることで、より洗練された花嫁姿を作り上げることができるのです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 掛下とは | 花嫁衣装の打掛の下に着る着物 |
| 掛下の役割 | 花嫁の美しさを引き立てる |
| 伝統的な掛下の色 | 白 (純粋無垢な心を表す) |
| 白無垢との組み合わせ | 白地の掛下が一般的 |
| 現代的な掛下の色 | 赤、桃色、金色、銀色など |
| 掛下の柄 | 鶴、亀、松竹梅などの吉祥文様、四季の花々、現代的なデザインなど |
| 掛下選びのポイント | 打掛との調和が大切 |
| 掛下と打掛の組み合わせ例 | 華やかな打掛には落ち着いた掛下、シンプルな打掛には華やかな掛下 |
掛下の着付け

掛下は、打掛を着る際の下に着る着物で、白無垢や色打掛に重ねて着用します。掛下の着付けは、一見すると振袖の着付けとよく似ていますが、おはしょりの処理に大きな違いがあります。
振袖を着る際には、おはしょりを作って着物の丈を調整するのが一般的です。しかし、掛下を着る際は、おはしょりを作りません。掛下の裾は、打掛の下から少し覗くように、長く引いて着付けます。これは、打掛の下から掛下の裾が少し見えることで、全体のシルエットに奥行きと優美さが生まれるためです。裾を引くことで、花嫁の立ち姿が一層美しく、優雅に見えます。
また、掛下の襟も重要なポイントです。掛下の襟は、打掛の襟から少し見えるように調整します。掛下の白く清潔感のある襟が覗くことで、花嫁の顔周りが華やかになり、清楚な美しさを引き立てます。
掛下の着付けは、これらの微妙な調整が必要となるため、熟練した着付け師の技術が欠かせません。経験豊富な着付け師は、花嫁の体型や着物とのバランス、そして好みに合わせて、掛下を美しく着付けてくれます。生地の質感や柄の見え方など、細部にまで気を配り、花嫁の個性を最大限に引き出す着付けを行います。そのため、花嫁は安心して着付けを任せることができ、特別な日を最高の装いで迎えることができます。
掛下の着付けは、単に着物を着るだけでなく、花嫁の美しさを引き立て、挙式全体の雰囲気を格調高く演出する重要な役割を担っています。まさに、日本の伝統的な婚礼衣装の美しさを支える、繊細で奥深い技術と言えるでしょう。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 掛下とは | 打掛の下に着る着物 |
| 掛下と振袖の違い | おはしょりの処理方法 振袖:おはしょりを作る 掛下:おはしょりを作らない(裾を長く引く) |
| 裾を長く引く理由 | 打掛の下から裾が少し見えることで、全体のシルエットに奥行きと優美さが生まれるため。花嫁の立ち姿を美しく優雅に見せる。 |
| 襟の処理 | 打掛の襟から掛下の襟が少し見えるように調整する。花嫁の顔周りを華やかにし、清楚な美しさを引き立てる。 |
| 着付けの技術 | 微妙な調整が必要なため、熟練した着付け師の技術が重要。花嫁の体型や好みに合わせて、個性を引き出す着付けを行う。 |
| 掛下の役割 | 花嫁の美しさを引き立て、挙式全体の雰囲気を格調高く演出する。日本の伝統的な婚礼衣装の美しさを支える技術。 |
掛下の歴史

掛下は、日本の花嫁衣装において、打掛の下に着用する着物です。その歴史は古く、平安時代にまで遡るとされています。平安貴族の女性が着用していた袿(うちき)が掛下の原型とされており、幾重にも重ね着することで華やかさを演出していました。袿は、袖の長くゆったりとしたシルエットが特徴で、生地の色合いや重ね方によって、身分や立場を表す役割も担っていました。
鎌倉時代に入ると、武家社会の到来とともに、打掛が婚礼衣装として登場します。打掛は、豪華な刺繍や織りで装飾された、重厚感のある着物です。この打掛の下に着る着物として、袿が変化し、現在の掛下の形へと近づいていきました。室町時代には、白無垢の打掛が登場し、掛下も白が主流となりました。白無垢は、純潔や清らかさを象徴する婚礼衣装として、現代まで受け継がれています。
江戸時代になると、婚礼衣装はさらに華やかさを増し、庶民の間でも打掛が着用されるようになりました。掛下も、より装飾的なものが登場し、刺繍や染めなど、様々な技法が用いられるようになりました。明治時代以降は、西洋文化の影響を受け、白いウェディングドレスが普及していきますが、伝統的な婚礼衣装である白無垢や色打掛、そして掛下も、日本の婚礼文化において重要な位置を占め続けています。
現代の掛下は、白無垢や色打掛に合わせて、様々な色や柄のものが選ばれています。伝統的な文様や、現代的なデザインのものなど、花嫁の好みに合わせて選ぶことができます。掛下は、花嫁衣装の美しさを引き立て、より一層華やかさを添えるとともに、日本の伝統的な婚礼文化を今に伝える、大切な役割を担っていると言えるでしょう。
| 時代 | 掛下 | 特徴 |
|---|---|---|
| 平安時代 | 袿(うちき) | 袖が長くゆったりとしたシルエット。重ね着で華やかさを演出。身分や立場を表す。 |
| 鎌倉時代 | 袿が変化 | 打掛が登場。袿が掛下の形へと近づく。 |
| 室町時代 | 白が主流 | 白無垢の打掛が登場。純潔や清らかさを象徴。 |
| 江戸時代 | 装飾的なものが登場 | 庶民にも打掛が普及。刺繍や染めなど様々な技法。 |
| 明治時代以降 | 様々な色や柄 | 西洋文化の影響でウェディングドレスが普及するも、掛下も重要な位置を占める。花嫁の好みに合わせて選べるように。 |
現代の掛下
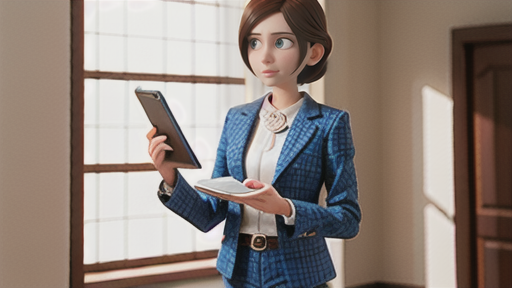
今の時代の花嫁衣裳のひとつ、掛下は、昔ながらの白いものだけでなく、色や模様、生地の種類も実に様々になっています。 例えば、淡い色合いの掛下や、刺繍やレースで飾られた掛下など、今の感覚に合ったデザインの掛下も人気です。
かつて掛下の生地は絹が主流でしたが、今ではポリエステルやレーヨンなど様々なものが使われるようになりました。これらの生地は絹に比べてお手入れが楽で、値段もお手頃なため、多くの花嫁に選ばれています。紅白の組み合わせや、金糸銀糸で彩られた豪華なものだけでなく、淡い桜色や空色、若草色など、多彩な色合いの掛下も登場しています。
刺繍やレース、織り模様も多様化し、古典的な花柄から、モダンな幾何学模様、可愛らしい動物のモチーフなど、花嫁の好みに合わせて選ぶことができます。生地の風合いも、艶やかな光沢のあるものから、マットな質感のもの、透け感のあるものまで様々です。
掛下の着こなし方も多様化しています。挙式では白無垢の下に白い掛下を着用し、披露宴で色打掛にお色直しをする際に、色掛下や柄掛下を合わせることで、ガラリと印象を変えることができます。また、白無垢に色掛下を合わせることで、さりげなく個性を演出する花嫁も増えています。
このように、今の掛下は伝統を守りながらも時代の変化に合わせて進化を続け、花嫁の個性や好みに合わせて様々な掛下を選ぶことができるようになりました。 掛下を選ぶ時間も、結婚式という特別な一日を彩る大切な思い出となるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 色・模様 | 白の他に、淡い色合い、刺繍・レース、金糸銀糸、桜色、空色、若草色など様々 |
| 生地 | 絹の他に、ポリエステル、レーヨンなど。お手入れが楽で価格もお手頃。風合いも光沢、マット、透け感など多様。 |
| 刺繍・レース・織り模様 | 古典的な花柄、モダンな幾何学模様、可愛らしい動物のモチーフなど |
| 着こなし方 | 挙式:白無垢に白掛下、披露宴:色打掛に色掛下・柄掛下 白無垢に色掛下で個性を演出 |
