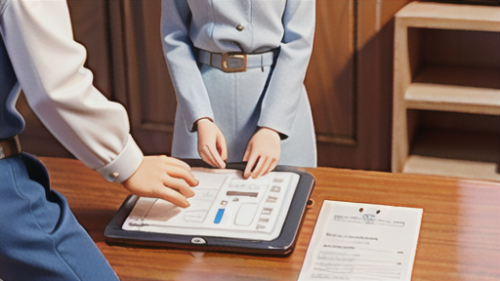和装
和装 十二単:雅な世界への誘い
十二単衣といえば、平安時代の王朝文化を象徴する華やかな装束として広く知られています。幾重にも重ねられた鮮やかな色の衣は、見る者を惹きつけ、優雅な世界へと誘います。多くの人は「十二単衣」という名前から、十二枚の着物を着ているとイメージするかもしれませんが、実際には必ずしもそうではありません。「十二単衣」は通称であり、正式には「女房装束」または「五衣唐衣裳」と呼ばれていました。
この装束は、平安時代から鎌倉時代にかけて宮中に仕える女性たちが着用していました。現代でイメージされる十二単衣は、主に平安時代の装束を指します。重ねる衣の枚数は、季節やTPO、そして着る人の身分や年齢によって異なり、五枚から二十枚ほどになることもありました。衣の色の組み合わせにも意味があり、季節や身分、場合によって使い分けられました。色の取り合わせは、襲の色目(かさねのいろめ)と呼ばれ、四季折々の自然の情景や、縁起の良いものを表現していたとされています。
十二単衣は、ただ着物を重ねて着るだけでなく、複雑な着付けの手順があります。まず、一番下に肌着を着て、その上に裳(も)というスカートのようなものを着ます。そして、袿(うちき)と呼ばれる着物と、表着である唐衣(からぎぬ)、さらにその上に羽織(はおり)を着ます。これらの着物は、それぞれ異なる色や柄で、重ね着によって美しいグラデーションを作り出します。現代においても、十二単衣は日本の伝統文化を象徴する衣装として、皇室の儀式や特別な場面で着用されています。また、時代劇や映画などでも見ることができ、国内外の人々から高い関心を集めています。その華やかさと歴史的な価値から、日本の美意識を伝える貴重な文化遺産と言えるでしょう。