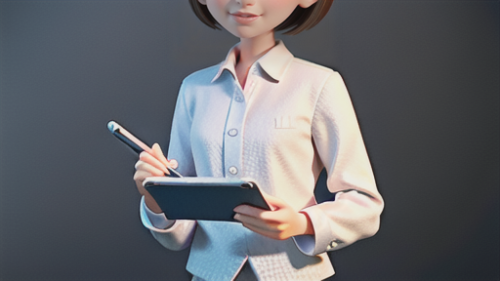 結婚準備
結婚準備 熨斗の意味と使い方:結婚における役割
熨斗(のし)は、お祝いごとの際に贈り物に添える飾りです。お祝いの席でよく見かける祝儀袋や贈答品の包み紙に印刷されていることがほとんどで、日本の伝統的な贈答文化には欠かせないものです。
熨斗の始まりは、古く貴重な食べ物と考えられていた鮑(あわび)にあります。鮑は長寿の象徴とされ、縁起物として大切に扱われていました。かつては、この鮑を薄く伸ばし乾燥させたものを贈り物に添えていましたが、時代とともに簡略化され、現在のような形になったと言われています。
熨斗は、右上にある飾り部分が特徴です。この部分は、かつて鮑を薄く伸ばした形をかたどった名残です。今では、印刷で表現されることが一般的ですが、その形は昔ながらの風習を今に伝えています。祝儀袋にのしを付ける場合は、水引という飾り紐と共に用いるのが習わしです。水引の色や結び方にも様々な種類があり、用途に合わせて使い分けられます。
熨斗を贈り物に添える意味は、贈る相手に敬意を表し、お祝いの気持ちを丁寧に伝えることにあります。結婚祝い、出産祝い、入学祝い、新築祝いなど様々なお祝い事で用いられ、お祝いの種類や贈る相手との関係性によって、熨斗紙の種類や表書きを使い分けることで、より真心が伝わる贈り物になります。
熨斗は、日本の伝統的な贈答文化を象徴する大切なものです。その歴史や意味を知ることで、贈り物への想いをより深く伝えることができます。単なる飾りではなく、感謝や祝福の気持ちを込めた贈り物の大切な一部として、日本の文化に根付いています。




