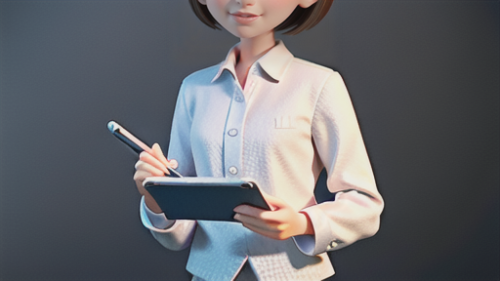結婚準備
結婚準備 祝儀袋の選び方と書き方
結婚という人生の大きな節目をお祝いする際に、お祝いの気持ちを表す贈り物として金銭を包む習慣があります。この金銭を包むために用いるのが祝儀袋です。祝儀袋は、単なるお金を入れる袋ではなく、贈る側の真心を伝える大切な役割を担っています。
祝儀袋は、いくつかの要素から構成されています。まず、水引は、人と人を結びつけるという意味があり、紅白や金銀などお祝いの種類によって色が異なります。結び方も様々で、一度結んだらほどけない結び方は、結婚のように一度きりであることを意味し、何度でも結び直せる結び方は、出産など何度あっても良いお祝い事に用います。次に、熨斗(のし)は、古くは鮑(あわび)を薄く伸ばしたものを贈り物に添えていましたが、現在では簡略化され、印刷されたものが一般的です。熨斗は、贈り物が神様への供え物であることを示し、神聖な贈り物であるという意味が込められています。そして、上包みは、水引や熨斗が印刷された外側の包みで、中包みには金銭を入れ、金額を記入します。表書きは、お祝いの種類に合わせて「寿」や「御結婚御祝」などと書きます。
これらの要素一つ一つに意味があり、古くからのしきたりが込められています。祝儀袋を選ぶ際には、これらの意味やマナーを理解し、相手に失礼のないように配慮することが大切です。目上の方や親しい間柄の方など、状況に応じて適切な祝儀袋を選び、真心を込めてお祝いの気持ちを伝えましょう。祝儀袋は、日本の伝統文化を反映した大切な贈り物といえます。