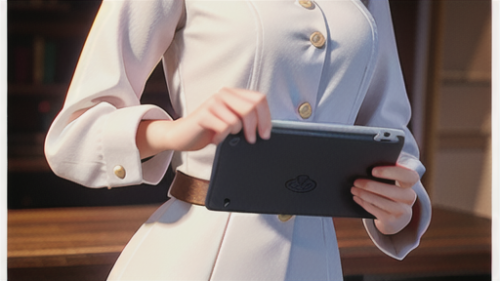 結納
結納 小袖料とは?結納金の基礎知識
結婚の儀式の一つである結納には、金銭や品物を贈り合う習慣があります。結納は、古くから伝わる日本の伝統的な儀式であり、両家が親族となることを正式に約束する大切な場です。
結納には、男性側から女性側へ贈るものと、女性側から男性側へ贈るものがあります。男性側から女性側へ贈る結納金は、結婚の準備資金として使われることが一般的です。この結納金は、地域によって呼び方が異なります。関東地方では「御帯料」(おんおびりょう)と呼ばれ、かつては帯などの贈り物に充てられていました。関西地方では「小袖料」(こそでりょう)と呼ばれ、小袖を作るための費用として贈られていました。
現代では、結納金は現金で贈られることが多くなっています。金額は両家の話し合いで決まり、決まった金額はありません。一般的には、男性側の収入や年齢、地域によって異なる場合が多いです。
一方、女性側から男性側へ贈る結納金は「御袴料」(おんはかまりょう)と呼ばれています。これは、袴を仕立てる費用として贈られていましたが、現代では男性側の結納返しの一部として使われることが多いです。結納返しの金額は、一般的に結納金の半額程度とされています。
結納金は、単なる金銭のやり取りではなく、結婚の意思を固め、両家の結びつきを強める象徴的な意味を持っています。結納の儀式を通して、両家は親族としての自覚を深め、新たな家族の誕生を祝います。結納金は、新しい人生の門出を祝う贈り物であり、両家の繁栄を願う気持ちの表れでもあります。





