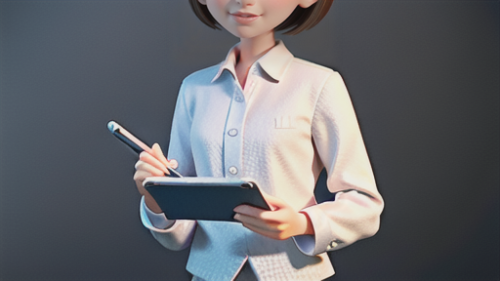新生活準備
新生活準備 贈り物選びの新しい形:リスト・ド・マリアージュ
結婚は人生の大きな節目であり、お祝い事の中でも特に喜ばしい出来事です。古くから日本では、結婚する二人を祝う気持ちを表すため、結婚祝いを贈る習慣があります。親しい友人や家族はもちろん、職場関係の人々もお祝いの品を贈り、新たな門出を祝います。贈り物を選ぶことは、祝福の気持ちを形にする大切な行為ですが、実は贈る側にとって悩ましいものでもあります。
まず、新郎新婦が本当に欲しいもの、必要なものを選ぶことが重要です。既に持っているものを贈ってしまったり、二人の趣味に合わないものを選んでしまうと、せっかくの贈り物も戸棚の奥に眠ってしまうかもしれません。最近は、新郎新婦が必要なものをリストアップした「欲しいものリスト」を共有するなど、贈る側が品物を選びやすい工夫もされています。贈る側としては、そうした情報を参考にしたり、新郎新婦の近しい人に相談したりするのも良いでしょう。
金額の相場も気になるところです。友人であれば3万円程度、親族の場合は5万円から10万円程度が一般的と言われています。ただし、それぞれの関係性や地域によっても異なるため、周りの人に相談しながら適切な金額を検討することが大切です。包む金額だけでなく、祝いの気持ちを伝えるメッセージを添えるのも忘れずに。手書きの温かい言葉は、贈り物と一緒に新郎新婦の心に響くでしょう。
結婚祝いは、単なる品物のやり取りではなく、二人の門出を心から祝福する気持ちの表れです。贈る側は、新郎新婦の立場に立って本当に喜んでもらえる贈り物を考え、受け取る側は、贈り物に込められた感謝の気持ちを受け止めましょう。そうすることで、結婚というお祝い事がより一層思い出深いものとなるでしょう。