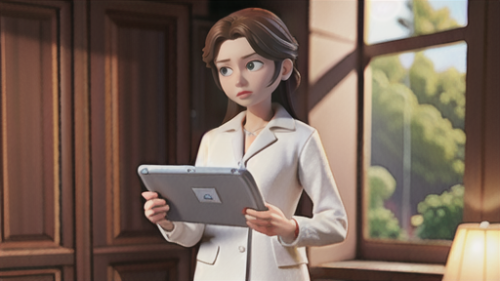和装
和装 婚礼に欠かせぬ筥迫:伝統の美
筥迫(はこせこ)は、日本の伝統的な婚礼衣装である打掛に合わせる、小さな飾り箱です。花嫁の胸元に差して用います。懐紙入れに形が似ていることから、懐紙入れと呼ぶ地方もあります。
その歴史は古く、江戸時代には既に武家の婚礼衣装の一部として使われていました。元々は、鏡や紅などの化粧道具や、懐紙、お守りといった小物を持ち歩くための実用的な袋でした。
当時は、袂(たもと)に様々なものを入れて持ち運ぶのが一般的でしたが、袂だけでは大切なものを入れておくには心許ないと考えられたのでしょう。そこで、小さな箱型の入れ物を紐で帯に結びつけて持ち歩くようになりました。これが筥迫の始まりと言われています。
時代が下るにつれて、筥迫は次第に装飾性を増し、婚礼衣装を彩る重要なものへと変化していきました。現代の筥迫は、金襴(きんらん)や緞子(どんす)、羅紗(らしゃ)といった美しい織物で作られ、華やかな刺繍や金箔、螺鈿(らでん)などで装飾されています。色とりどりの飾り房もあしらわれ、豪華な仕上がりとなっています。
筥迫の文様には、松竹梅や鶴亀、鳳凰など、縁起の良いものが多く用いられます。これらは、子孫繁栄や長寿など、結婚における幸福への願いが込められたものです。
筥迫は、花嫁の美しさを一層引き立てるだけでなく、日本の伝統や文化を象徴する美しい工芸品と言えるでしょう。婚礼衣装の中で、花嫁の胸元に華を添える筥迫は、古き良き日本の風習を今に伝える大切な存在です。